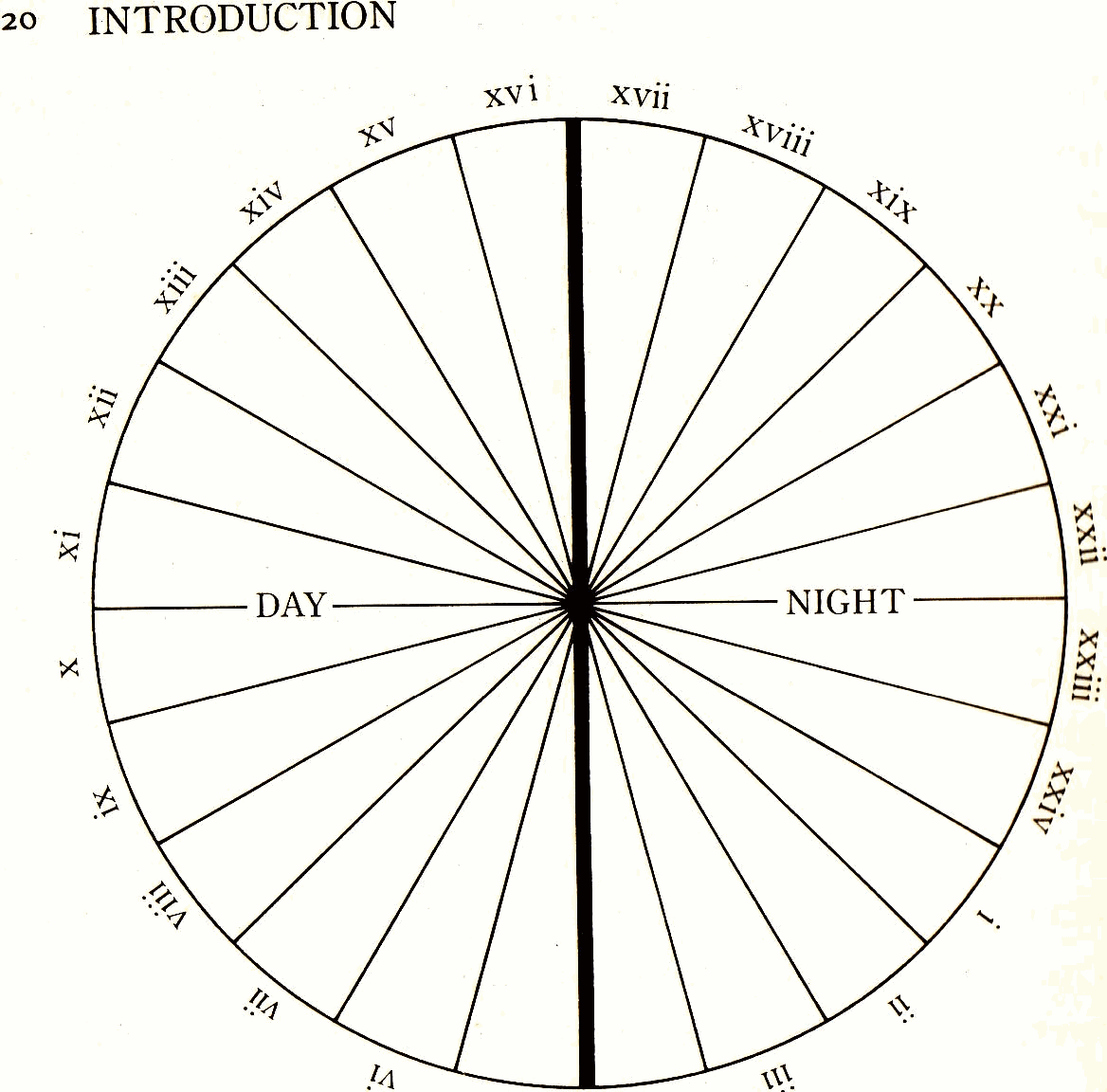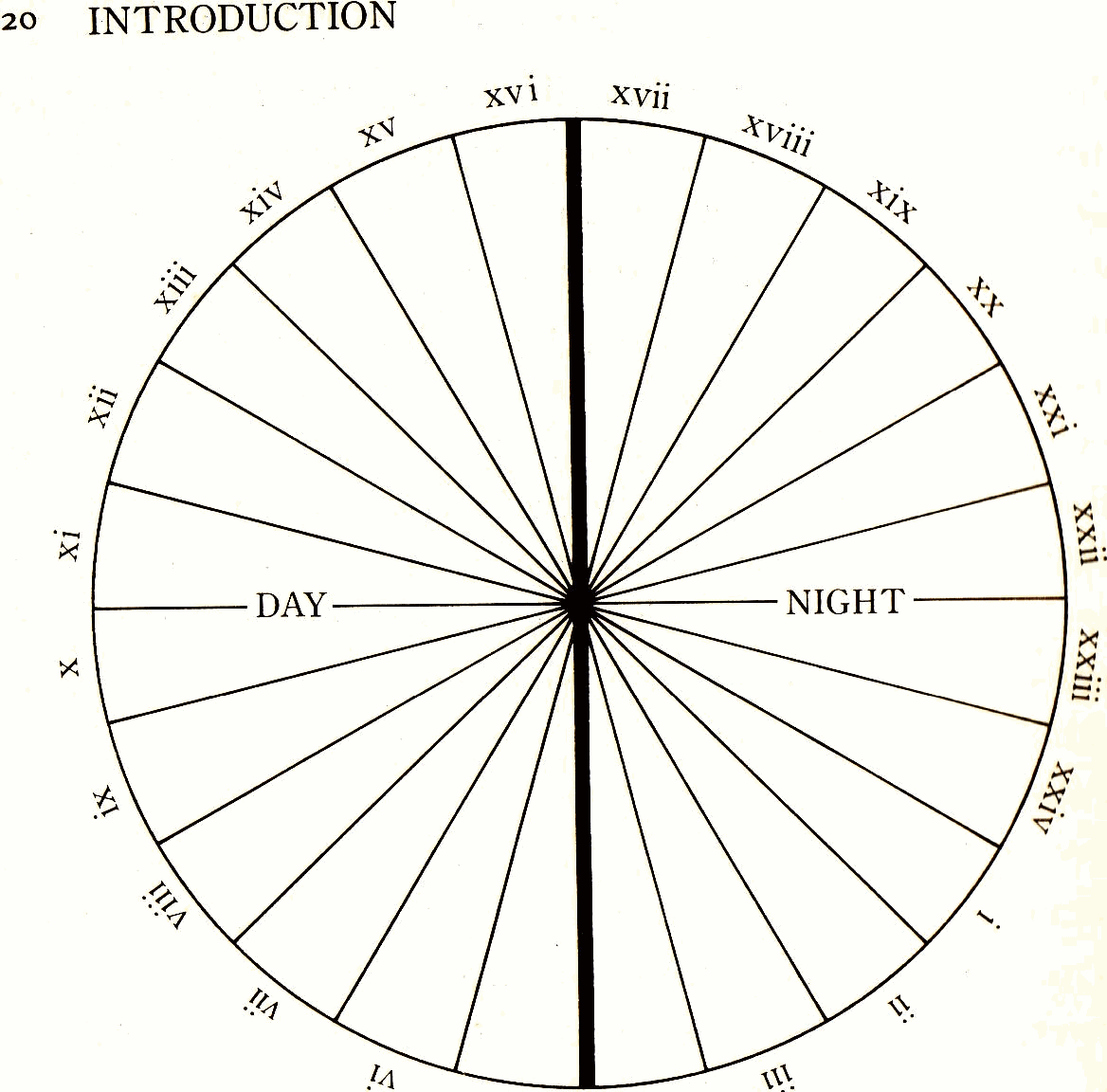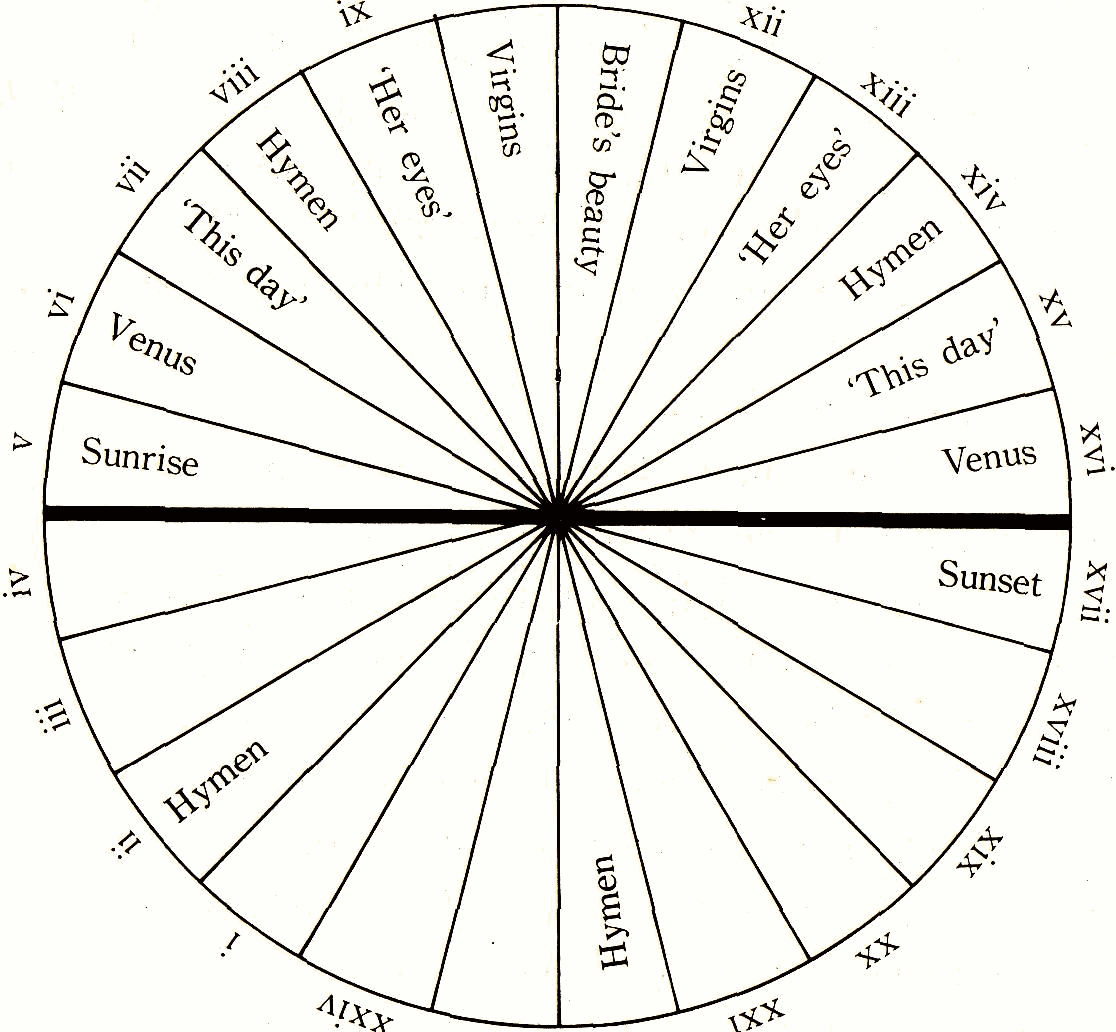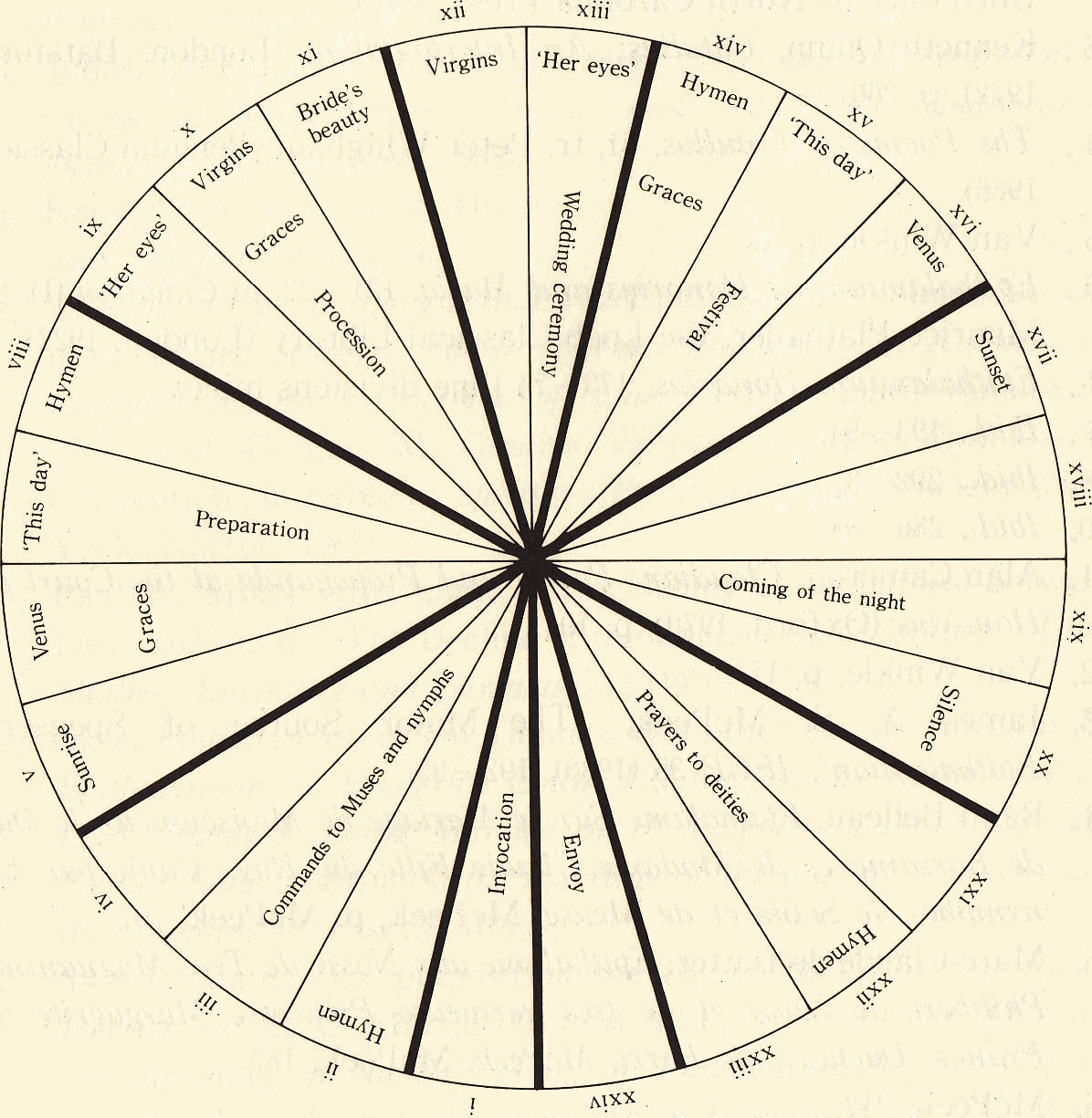『祝婚歌』と優美の女神たち
その数秘と図像について
初めに、スペンサーの『祝婚歌』(Epithalamion)に表れる数秘について触れ、その後で、優美の女神たち(the Graces)の図像について述べてから、この作品に秘められている彼女たちの図像の意味を考えてみたい。
図(1)は、『祝婚歌』全体の構造を図式化したものである。円の外側のローマ数字の番号は、この作品が全部で24スタンザから成り立つことを示している。『祝婚歌』は、スペンサー自身が自分の結婚を祝うために書いた。彼は、1594年6月11日の夏至の日に(これは現在の暦よりも約11日早くなっている)、エリザベス・ボイル(Elizabeth Boyle)と式を挙げた。各スタンザは18〜19行(15スタンザは17行)で、最後の24スタンザのみ7行となっている。24は、結婚日の明け方から深夜に及ぶ24時間を表し、第5スタンザで太陽が昇り、第17スタンザの5行目で夜が始まり、このスタンザを境にスタンザの最後の行にある折り返しがそれまでと変わる構成になっている。ケント・ハイヤット(Kent Hieatt)によれば、昼は第1スタンザに始まり、昼の総スタンザ数16と4分の1、夜の総スタンザ数7と4分の3は、スペンサーたちが結婚した日の南アイルランドでの昼と夜の長さにぴったり一致していると言う(1)。しかし、『祝婚歌』の昼と夜の分け方、またその時間の解釈については必ずしも説が一致しているわけではない。
図(1)
昼と夜のスタンザ構成
昼と夜のもう一つの分け方によれば、第1スタンザから第4スタンザまでを夜明け前と見なして、これらを夜の部分に数える仕方である。この数え方だと、日の出が第5スタンザに始まるので、日の出から日没までがちょうど12スタンザとなり、これらを昼と考えれば、昼と夜とが12ずつの対称形を形成する(図ではivスタンザとvスタンザが空白になっている)。この見方だと、夜の時間帯が、明け方の四つ(1〜4スタンザ)と結婚の初夜の八つ(17〜24スタンザ)というように、1対2の比率で分割する形になる(2)。さらに、この分け方だと、第1スタンザと第13スタンザ、第2スタンザと第14スタンザのように、互いに対称し合うスタンザが、類似するイメジャリによって内容的にも対応している点をうまく説明できる。対称形も1対2の比率もスペンサーにとって重要な概念であるから、彼は、これら二通りの仕方で、昼と夜の分割をだぶらせていると考えていいと思う。『祝婚歌』の第6スタンザを引用しよう。
僕の愛する人は、今夢から覚める。
その麗しい目は、薄暗い雲にかすむ星が、
今その美しい光を放つようだ
ヘスペラスが頭をもたげるよりもなお輝かしく。
さあ貴方たち、喜びの娘たちよ、来て
素早く彼女を飾ってください。(短)
だがその前に来るがよい、麗しの時節たちよ、貴方たちは
ジュピターの楽しい楽園で昼と夜から生まれ、
年毎の季節を割り当て、
この世の麗しいものをことごとく
絶えず造り出し新たにする。(短)
次いでキプロスの女王に仕える三人の乙女たちよ
僕のいとも美しい花嫁を飾り
着飾らせながら、その合間に
時折優美を見せてください
(短)
またヴィーナスにするように彼女にも歌ってください
森もこれに応えて、貴方たちのこだまを響かせましょう。
『祝婚歌』の各スタンザは、通常、ここに見るように、5歩格(pentameter)の長行の間に3歩格(trimeter)の短行3行が混じり、それらが、各スタンザの長行を四つのグループに分割している。多少の不統一はあるものの(4)、このような短行が全部で68行あり、これによって長行が92のグループに刻まれることになる。長行は全部で365行あり、これが1年を意味することはすぐに分かる。ところが、長行は第23スタンザの終わりでちょうど359行となり、詩の内容もここで終わっていて、第24スタンザには後書きとしてEnvoyが来ている。
地球の公転と自転のために、1日に恒星が天球を360度回る間に太陽は359度回り、したがって恒星時は太陽時よりも1日に1度ずつ短くなる。このことから、ハイヤットは、『祝婚歌』の時間は恒星時を表わしていると見る(5)。しかし、日の出と日没とを基準とする昼と夜の分け方からすれば、ここでの時間は太陽時を意味すると解することも当然できるわけで、これを恒星時だけに限定することはできない。いずれにせよ、24が1日を、365が1年を意味することに変わりはない。その上さらに、最後の第24スタンザの長さが半分であることから、正確にはスタンザの総数は23と2分の1になる。この数が赤道に対して太陽の黄道のとる傾きと一致していることから、ここでは、天の赤道と天の黄道をめぐる太陽の二重の運行が示唆されていると解することができる(6)。
長行のグループ数「92」についても説が分かれるが(7)、当時の暦の通念にしたがって、1年を4季に分けて、「92」は夏至から秋分までの日数を表わしていると見るのが妥当であろう(8)。これで昼と夜が、16対7(夏至)、12対12(秋分)の二通りに分けられているのとうまく呼応することになる。
このように見ると、『祝婚歌』の数秘は、1日の時間数、1年の日数、夏至から秋分までの季節、太陽の日周と黄道の二重の運行、それに恒星の運行などを秘めて、テキスト本文の背景を織りなしているのが理解できる。ところで、この時間の数秘は、『妖精の女王』の第7巻(7篇28〜46スタンザ)に登場する「変転」(mutabilitie)のペイジェントが下敷きになっていると考えられている。そこでは、4大元素、4季、12カ月、昼と夜、生と死などが登場し、さらに七つの惑星と恒星も出てきて、これらの巡りの下での人間の営みが描かれている。「変転の巻」では、全てを巻き込んで一切を無に帰していく「変転」と、彼の支配の下で営まれる人間の労働の意味が問われるが、最期には、終末的な解決によって「変転」のアレゴリーであるタイタネス(Titaness)が敗北することになる。スペンサーがこのペイジェントを描くに当たっては、すでに広く知られていた図像、例えばスティーブン・ホーズ(Stephen Hawes)のPastime of Pleasureの版画(9)に見られるような「時間の図像」が念頭にあったと思われる。「時間」は、髭を生やし、両手に時計と焼き尽くす炎を持ち、鎌の代わりに剣を腰に差し、太陽と月を帯び、翼を広げ(翼は四季を、その羽毛は12か月を意味する)、身に惑星を帯びている。
「変転」が繰り広げるペイジェントの中で、昼と夜に続いて時節の女神たち(the Hours)が登場する。彼女たちは、天球の門を守りながら天と地を秩序づける役目をしている(『妖精の女王』7巻2篇45スタンザ)。しかしながら、ここでは、彼女たちさえも、「変転」の渦に巻き込まれてしまっている。彼女たちは、ホメーロスの『イーリアス』(5巻749〜50行)に出てくる季節の女神たち、ホーライに起源を持つのであろう。『祝婚歌』においては、時節の女神たちは、「変転」に巻き込まれるのではなく、むしろ、天体の運行を秩序付け、結婚の1日を祝福するという肯定的で重要な役割を果たしている。『祝婚歌』の時節の女神たちのこのような高い地位は、ヘーシオドスの『神統記』(901〜4行)に見られる。ここでは、ホーライは三人で、「秩序」(Eunomia)「正義」(Dike)「平和」(Eirene)と名付けられ、死すべき人間の労働を守る役割をしているからである。
ここで、優美の女神たちに目を移すと、わたしがこの優美の女神たちの図像を選んだ理由の一つは、これが、古典時代からスペンサーの時代に至るまで比較的一貫した構図を保っているからである。彼女たちが神話的に明確な形を取るのは、やはり『神統記』においてである。そこで彼女たちは、ホーラたちのすぐ後ろで、カリスたち(Charites)として登場し、その数も3人に限定され、アグライアー(Aglaia)「輝く女」、エウプロシュネー(Euphrosyne)「喜び」、タレイア(Thaleia)「花の盛り」と呼ばれている(『神統記』9
07〜11行)。そこでは、彼女たちは、詩歌の女神ムーサたちや恋心の神と共にオリュンポスに住み、祝祭の賑わいのうちにムーサたちの歌声に加わっている。ついでながら、彼女たちの歌を大地が「こだました」とあるのも『祝婚歌』の「折り返し」(リフレイン)を思わせる。
ここで優美の女神たちの哲学的な背景、すなわち「3」という数に触れてみよう。スペンサーの「数」には、天文と同時に哲学、特にピタゴラス派の背景があると言われている(10)。この派の影響は、プラトンに始まりプロティノスたちを経てルネサンスに及ぶのであるが、ピタゴラス派によれば、万物の本質は「数」であり、「宇宙の魂」から物体に至るまでの万物が、「数それ自体」によって構成されていると考えられていた(11)。「1」は根元であって空間を持たない。これが「2」と成ることによって二つの点を結ぶ線が生まれ、「2」が「3」と成ることによって三角形の点を結ぶ線から面ができ、「3」から「4」となって、三角形を底辺に四つ目の頂点を結ぶピラミッドの立体(三角錐)が構成される。すなわち、「1」なる非空間的な原初から立体に至るまでが、「運動する数」(12)によって形成されていくと考えられている。
ピタゴラス派は、この数の「流れ・流転・運動(flux)・拡大(extension)」に宇宙生成の原理を見ているとわたしは理解している。この原理から、プラトンの『ティマエウス』に出てくるように、4大元素は数による三角形によって構成され(『ティマエウス』53)、火は正四面体(ピラミッド)、土は正六面体(立方体)、空気は正八面体、水は正二〇面体であり、さらに宇宙はもっと複雑な多面体となっていく(『ティマエウス』54〜55)。「目に見えるものは数である」というピタゴラス派の原理では、調和を生み出す「数の割合・比率」(Gr.logos;Lat.ratio)も重視されることになる(13)。
「数の運動」はさらに「時間」と密接に関連してくる。
プラトンは、『ティマエウス』で、「時間」を「数に即して動きながら永遠を映す天体の運行」(37D)と定義して、「永遠を模倣し、数に即して円運動をする時間の姿」(38A)である天体の運行こそ最も崇高なものだと考えている。プラトンはまた、天の赤道と天の黄道の二つの円を組み合わせて、「天の体と天の魂の組織」を説明しようとしているが(36DE)、これも『祝婚歌』の数秘を思わせる(14)。プラトンによれば、恒星の運行は我々の魂に永遠を示し、真の美徳を教えるものである(47BC)。この見方は、「数」と「美徳」とを結びつけるもので、優美の女神たちの図像を考える上で注意すべきであろう。
「3」という数については、アリストテレスも、ピタゴラス派に準じて、「全宇宙もそのうちにある万物も3によって限定されている」と述べていて(15)、この考え方はプロティノス(Plotinus)に至って一層明確に秩序づけられる。彼は、その論集の一つ「三つの原理的なものについて」において、「1」なるものと、知性と、魂の三段階を区別して、美は「1」なるものの本性として知性と魂とを照らし、魂はこの美を「観る」ことによって根元なるものに近づくと強調する(16)。プロティノスには神話が多く取り入れられているが、『祝婚歌』との関連で興味深いのは、ディオーネーの娘としての地上のアプロディテーが、結婚の守り神とされている点である(17)。
優美の女神たちの図像に入ることにする。図(2)は、よく知られたポンペイで発見された優美の女神たちの図像である(18)。セネカは、彼女たちが時節の女神たちの妹でヴィーナスの侍女であり、彼女たちが手を取り合っているのは、「善行(beneficii)は、与えることと受けることと返すこととが結び合っていなければならないからだ」と述べている。この解釈はずいぶん古くからあったようで、この女神たちの図像の基本的な性格としてそれ以後も変わらない。セネカは、彼女たちが薄い衣をまとっていると言っているが、ここでは裸身である。ホラティウス(Horatius)のオード(7、19)では、この女神(Gratia)は裸身と薄い衣をまとった場合の両方が出てくる。手に穂を持っているのは、彼女たちの起源が豊穣の女神であった証拠であろうか。エドガー・ウイント(Edgar Wind)によれば(20)、このセネカの解釈に、セルウィウス(Servius)は、さらに「3人のうち、1人が後ろを向き二人が前を向いているのは、わたしたちから出る一つの善行は二つになって返ってくるからだ」という解釈を加えている。
図(2)
ポンペイの優美の女神たち
ポンペイの優美の女神たちの図像は、ルネサンスにもそのままの構図で受け継がれている。そのよい例が二つある。フィレンツェのピコ・デラ・ミランドーラ(Pico della Mirandola,1463-94)のメダルの裏の図像とロレンツォ・トルナブオーニ(Lorenzo Tornabuoni)の妻ジョバンナ(Giovanna)のメダルである(21)。ピコの思想はフィチーノ(Marsilio Ficino)と必ずしも同じではないが、ここにはフィチーノの哲学がよく表われている。ピコのメダルには、3人の女神の寓意を表わす言葉が刻まれていて、それは、左側が「美」(Pulchritudo)、中央が「愛」(Amor)、右側が「喜び」(Voluptas)となっている。フィチーノも、ピタゴラス派に従って「3」を万物の尺度と考えていたようで(これはキリスト教の三位一体論とも結びつく)(22)。「美」は神の中に生じ、「愛」は世界をこの「美」に向かわせ、創造主の元に戻るところに生じるとして、この三者の円運動に優美の女神たちの踊りの輪を結びつけている(23)。
フィチーノによれば、「優美」(Gratiae)とは「調和」を意味し、これには、魂の優美(すなわち調和した美徳)、身体・物体の優美(調和した色と線)、音の優美(調和した音)の三種類があり、魂の美徳は知性によって、身体の美は視覚によって、音の美は聴覚によって認識される(24)。「愛は美に始まり喜びに終わる」から、真ん中の「愛」は顔を右に向けている。ここには、「1」である神からの「流出」(meatio)、魂によるこれの「受容」(raptio)、神への「逆流」(remeatio)というルネサンス・ネオプラトニズムの中心概念が、「与える・受ける・返す」の3拍子によって表現されており、同時に真ん中の「愛」は、「美」と「喜び」とを二重に受けるというセルウィウスの解釈をも暗示している(25)。
次に、ロレンツォ・トルナブオーニ(Lorenzo Tornabuoni)の妻ジョバンナ(Giovanna)のメダルと、ポリツィアーノ(Poliziano)の妹、マリア・ポリツィアーナ(Maria Poliziana)の二人のメダルを見てみよう。ジョバンナのメダルには、左が「貞節」(Castitas)、中央が「美」(Pulchritudo)、右側が「愛」(Amor)とあり、ここでは「喜び」が消えて、その代わりに「貞節」が現われる。「美」は「愛」の方に顔を向けながら、手を「貞節」の肩に掛け、互いに顔を背け合っている「愛」と「貞節」とを調和させているのが分かる。ピコのは男性的であるのに対して、こちらは女性的な図像であると言える(26)。
(Castitas) (Pulchritudo)(Amor)
ジョバンナ(Giovanna)のメダル
マリアのメダルでは、片面では優美の女神たちが「協調」(Concordia)の文字とともに刻まれ、その裏面には、投げ矢を手に持ち、柱(実は投げ矢の束)にもたれかかった半裸の女性が描かれていて、「不動」(Constantia)と書いてある。コンスタンティアは、通常長い槍を手にして柱に持たれる貞節の化身であるから、槍の代わりに投げ矢(すなわち愛の矢)を持つこの半裸の女性は、コンスタンティアとヴィーナスとの合体した姿、Venus-Virgoであるとウイントは解釈する。ところが彼女は、柱の代わりに「協調」を意味する束ねた投げ矢、すなわち優美の女神たちにもたれているのである。このことから、彼女は、反対面に刻まれた3人の女神たちの統一体であり、女神たちは、彼女の三つの働きを体現しているとウイントは指摘している(27)。彼女を頂点とするこの構成は、先のピタゴラスの「4」という数字が構成する三角錐を思い出させる。
(Constantia) (Concordia)
マリアのメダル
図(3)は、よく知られたボッティチェルリ(Botticelli)の「春」(Primavera)の女神たちであるが、これについては、プラトンの『シュンポジアム』に付けたフィチーノの注解(5章2節)が、最も適切な解説になると思う。フィチーノによれば、天上の美は、美徳と形と音とに宿り、これらを認識する魂の働きも、理性と視覚と聴覚であり、魂は、この三つの働きを通じて、美を愛しこれに呼び寄せられる。フィチーノは、この三つの働きに対応させて、優美の女神たちを「美の輝き」(Splendor=Splendour)「活力・若さ」(Viriditas=Youth)「歓喜」(Laetitia=Happiness)としてそれぞれに割り当てている(28)。ウイントによると、図の左に、髪を垂らし大きなブローチを着け、うっとりと官能的な姿を見せているのが「喜び」(Voluptas)で、飾りを着けず髪を束ね、やや硬い表情でこれと向き合っているのが「若さと活力」(Castitas)で、右で髪を美しく編み少し小さな飾りを着け、気品を備えて二人をリードしているのが「美の輝き」(Pulchritudo)である。フィチーノに従って、「喜び」は聴覚を「若さ」は視覚をも意味するとすれば、二人は互いに反発と協調の可能性を秘めて向き合い、これを「美」の理性が均衡させていることになる。「若さ」が真ん中にいるのは、愛において未熟な「貞節」が「喜び」と「美」から教えを受けているからであろうか。彼女の上に二人がちょうど冠のように手を組んでいるのが象徴的である(29)。
 図(3)
図(3)
( ボッティチェルリの春の優美の女神たち)
スペンサーの優美の女神たちは、『羊飼いの暦』(The Shpheardes Calender)の「4月」(113〜17行)の中で、エリザベス女王を讃える歌に登場する。
対になって踊るには、四人目のグレイスが要るではないか。
その席を僕の女王にも等しく得させて
彼女をば優美の女神とし
四番目の席を満たして
他の女神たちと共に天にあって治めさせよう。
ここでは、エリザベス女王が4人目の女神として登場する。『羊飼いの暦』にはE.K.(Edward Kirke?)と称する人の注がついていて、ここの所に「彼女はジュピターの娘であり・・・・・詩人たちは、彼女たちをあらゆる美と麗しさの女神となし、それ故に3人とする。すなわち、第一に、人々は他人に対して惜しむことなく恵み深く寛大に与えるべきこと、第二に、他人からの賜物は礼を尽くして受けるべきこと、第三に、感謝してそれに報いるべきこと」とあり、「彼女たちが裸の姿で、1人がわたしたちの方を向いているのは、わたしたちが与えた賜物は、二重の感謝に値するからだ」とある。
また、「四月」の版画に描かれた女王については、詩の末尾にウェルギリウスの『アエネーイス』(1巻327〜28行)からの引用があり(30)、これにもE.K.が注して「イーニアスが、ダイアナの侍女の姿をして現われたヴィーナスに向かって言う言葉」とある。これで、ここに登場するエリザベス女王は、ヴィーナスとダイアナの合体したもの、先のコンスタンティアと同じくVenus-Virgoであることが分かる(31)。このように見てくると、スペンサーの図像は、大陸の伝統に従いながらも、セネカとセルウィウスの古典に忠実であり、しかも独自の意味が重ねられているイギリス特有のものであると言えよう。
今度は、『妖精の女王』(6巻10篇12節)から、よく知られた女神たちの図像を引用しよう。
外側の者たちはみんな輪になって
ぐるぐる踊る。だがその真ん中には
別の三人の乙女が歌いつつ踊っていた。
他の者は、彼女たちを取り囲み
ちょうど花輪をつくるように回っていた。
このまた真ん中にいるのは
もう一人の貴婦人、まるで高価な宝石のようで
豪華にちりばめられた宝石の指輪の真ん中にあり
その麗しい輝きを周りのすべてに及ぼしていた。
これは礼節の騎士キャリドアが垣間見た場面である。これに続くスタンザによると、3人の名前は『神統記』の通りである。しかし、4人目は、アリアドネーの冠をかむっていて(同13スタンザ)(32)、ちょうど「春」に出てくる「貞節」を思わせ、「神にも似た姿、めったに見られぬ至高の美しさ」と「確固とした貞節」(27スタンザ)で飾られている。女神たちは「喜びの娘たち、ヴィーナスの侍女」(同15スタンザ)と呼ばれ、また、ここの12スタンザには、『祝婚歌』に繰り返し用いられる "ring" "sing" "dance" 、それに "garland" も出てくる。同10スタンザでは、『祝婚歌』の折り返しと同じような「彼らのこだまが森中に響きわたった」も現われる。
しかしながら、ここでの4人目の女神には、『羊飼いの暦』をも含めて、今までに見られなかった一つの特徴が加えられているのに気がつく。それは、スペンサー自身が羊飼いとなり、詩の中で「彼女一人のために」「今までだれも奏したことがないほど楽しく」歌っていることからも分かるとおり、彼女には、スペンサーのプロポーズの相手、エリザベス・ボイルのイメージが重ねられていることである(33)。求愛と結婚の優美の女神たちがここに姿を現わしてくる。
もう1度、『祝婚歌』の第6スタンザに戻ろう。ここでも優美の女神たちは「喜びの娘たち」(96行)と呼ばれ、ヴィーナスの3人の侍女として、時節の女神たちと共に登場している。彼女たちのことは、第10スタンザでは「美しい優美」とやや暗示的に示されるし、第14スタンザにもアリアドネーの夫バッコスと共に「優美の女神たちに踊らせよ」とある。図(1)を見ると分かるように、第5スタンザから第16スタンザまでの昼のスタンザの間に、優美の女神たちは第6、第10、第14の各スタンザに姿を見せて、「その合間に/時折優美を見せてください」(107行)とある本文を裏付けている。彼女たちは、昼のスタンザを三つに分け、その上、それぞれのスタンザ群を「5・G・7・8/9・G・11・12/13・G・15・16」のように、調和を表わす1対2というピタゴラス以来の最も基本的な比率に刻んでいる。
図(1)に見るように、日の出から日没に至る昼間のスタンザにも、同一の表現やイメージが対称形を構成して用いられている。ヴィーナスはプロティノスにもあるように結婚の守護神であり、第7と第15スタンザの「この日」は、太陽の巡りの下での「結婚の一日」を意味し、ハイメンは言うまでもなく結婚の日そのものを導く役割をする。このアーチ型のイメジャリの頂点に現われるのが、第12スタンザの花嫁が体現する「内なる美」(186行)とこれを仰ぐ「貞節」な「処女たち」(181行と212行)と花嫁の「目」(159行と234行)である。頂点に位する「内なる美」は、「だれも見ることができないほどに高い天上の賜で飾られ」(187行)ている。これらの「美」と「美を愛する目」と「(貞節な)処女たち」は、スペンサー独自のネオプラトニズムを示唆している。しかも、この三つの美徳を備えた「花嫁」は、4人目の優美の女神として、イメジャリ全体の中心的な位置を占めているのが分かる。もっとも、彼女は、これまでのどの優美の女神たちよりも宗教的な性格を濃く帯びてはいるが。
このように見てくると、日の出と日没に象徴される地上を底辺にして、天の最高位の美に至るイメジャリがアーチ型を構成して、女神たちの踊りの「輪」"ring" と共に回りながら、天と地との間に調和を「こだまさせ」"ring" ているという構図が浮かび上がってくる。
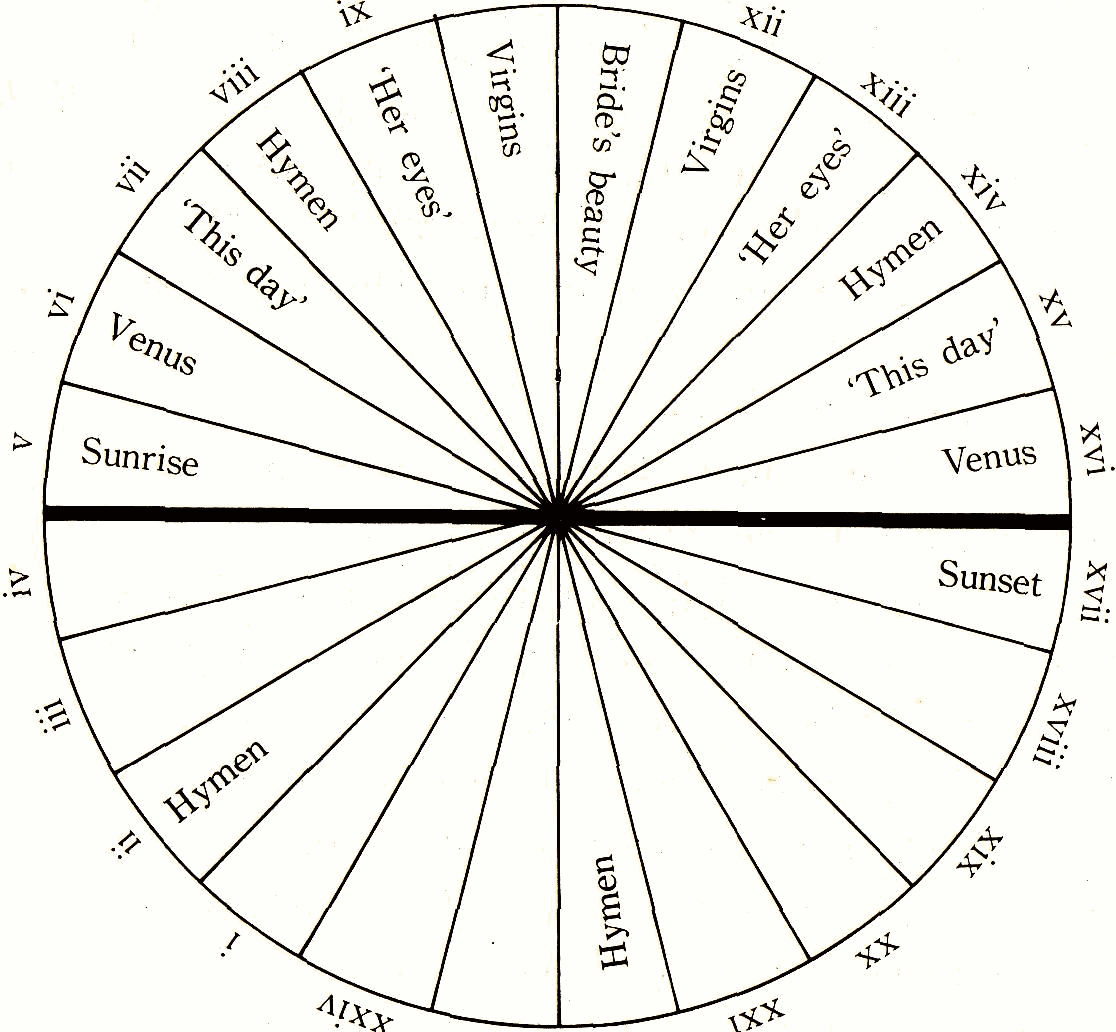
(xiスタンザ "Bride's beauty" 頂点にして各スタンザに対称形に同一の表象が表れる。)
(優美の女神たちは、第6と第10と第14スタンザに出てくる。)
一方で、結婚式自体は、第1スタンザのミューズたちへの呼びかけに始まり、妖精たちへの招待、花嫁の身支度、行列、挙式、祝宴、夜へと進行していく。この進行そのものも、図(1)に示されるように、第12スタンザと第13スタンザの挙式を中心にして、左右が対応し合う。地上で進行する祝典に呼応するように、時節の女神たちは、天において神々の運行を司り、『神統記』の名前の通りに「秩序」と「正義」と「平和」を地上にもたらす。第6スタンザで、「喜びの娘たちよ」と優美の女神たちに呼びかけてから、急に「待て、その前に時節の女神たちよ、先に来なさい」とある真意もこの辺にあると思われる。優美の女神たちは、この時節の女神たちと一緒になって、地上と天上との間に「調和」を「響かせ」ていることが、折り返しの "sing" と "ring" の押韻によって暗示されているのであろう。
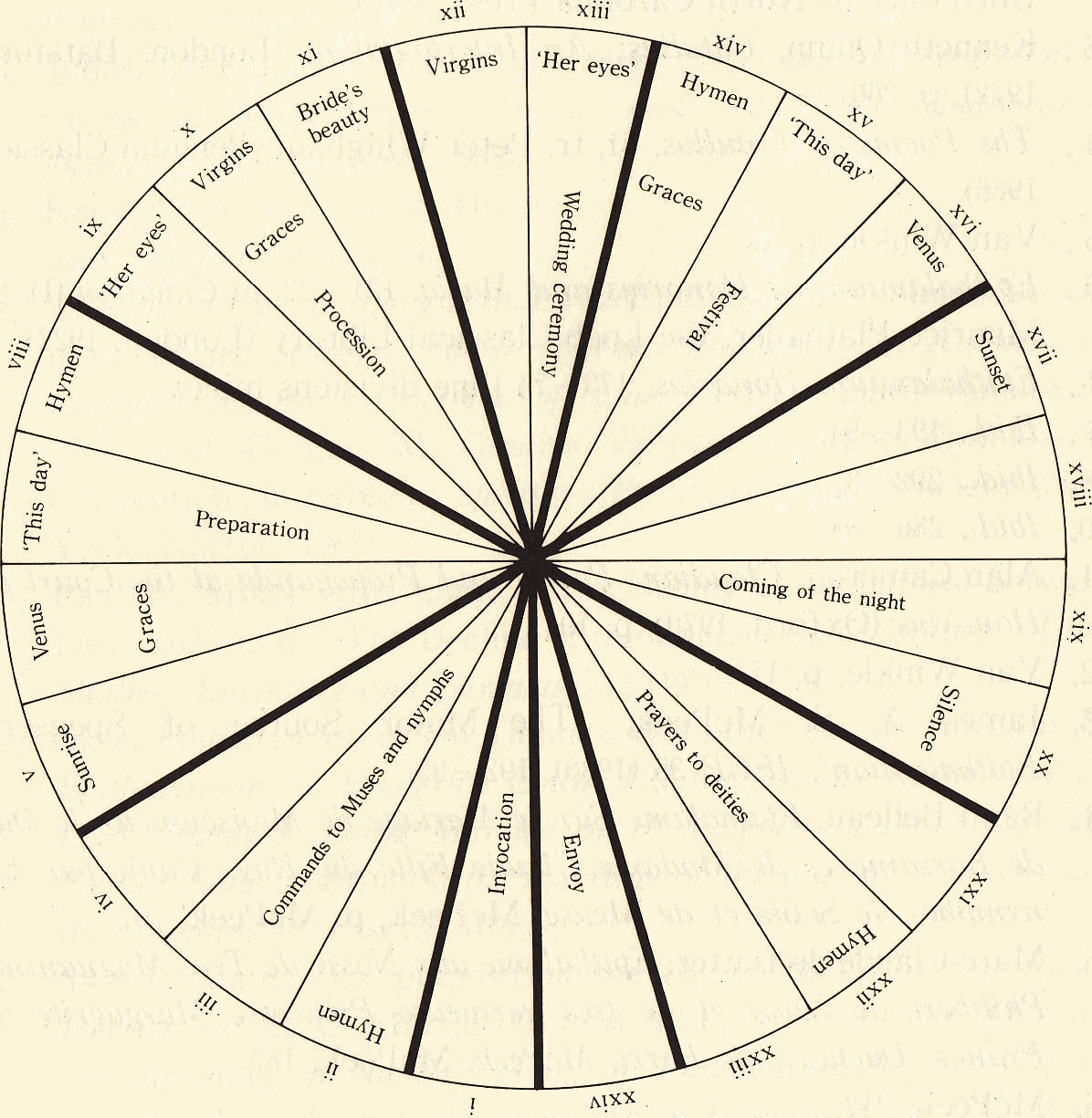
『祝婚歌』全体の表象の配置
以上大変おおざっぱに、『祝婚歌』の数秘の大要と優美の女神たちの図像について述べてみた。これだけでも分かるとおり、スペンサーの作品では、数秘、図像、神話、哲学、天文、占星術などが、渾然一体となってテキストの背後に織り込まれている。言うまでもないが、このような図像や数秘を解明するには、恣意的な判断や勝手な「読み込み」をしないように注意しなければならない。特に、こういう手法で用いられるシンボリズムは、テキストの背後にさりげなく隠されている場合が多いのでなおさらこの点に留意する必要があろう。このようなシンボリズムを解明する心構えとしては、テキストの表層に表われた意味と数秘的な解釈とが密接に関連づけられていなければならないことである。概して、図像や数秘は、従来までのテキストの解釈を支え、これを補強するものではあっても、従来の解釈を根底から覆すような性質のものではない。少なくとも、そういう心構えで数秘や図像を扱わなければ危険が伴うとわたしは考えている。
スペンサーのテキストを読むときに、わたしは二重の作業が同時に行なわれているように思えてならない。すなわち、テキストの表層を表層として受けとめる作業と、同時にそれを深層の消息を表わす記号とみなす作業とである。テキストの背後から支える天文学的・哲学的な数と言葉による図像が、テキスト本文と結びつくとき、そこに、古代からの神話的な宇宙観とでも言うべきものが浮かび上がってくる。それは、魂の世界と結びついた宇宙の精神とでも言うべきものである。思うに、スペンサーの描こうとした宇宙の姿とこれが生み出す生命の実相、さらにこれらを表現するアレゴリーは、文学作品をその全体として統一のとれた構成へとまとめるにはなはだやりにくい主題と手法ではないだろうか。これほど奥行きの深いテーマを彼独特のアレゴリーによって成功させるには、よほど明確な構成理念を前もって確立しておかなければ、作品全体の統一が崩れるのではないかと思われる。この意味でも、数秘とは、スペンサーが作品を構成するために、どうしても採らなくてはならない手法であったのかもしれない。
(この論文は、第58回日本英文学会のスペンサー・シンポジアムでの発表に基づいて書かれた論文「Epithalamionにおける時間の数秘と優美の女神たち」『英文学試論』第9号、1987年、に加筆訂正したものである。)
【注】
(1)A.Kent Hieatt, Short Time's Endless Monument: The symbolism to the
numbers in Edmund Spenser's Epithalamion. ( New York: Columbia University Press,1960)p.10.
(2)Alastair Fowler, Triumphal Forms: Structural patterns in Elizabethan poetry.(Cambridge: At the University Press,1970) pp.162-65.
ファウラー とハイヤットとの最も大きな食い違いは、「昼のスタンザ」をどこから始めるのかという点にある。ハイヤットは第1〜16スタンザを昼と見ているのに対し、ファウラーは実際の日の出(第5スタンザ)をその日の始まりと見る。この数え方は、『妖精の女王』でスペンサーが用いている分割法で、しかも、『妖精の女王』の数は、1日を昼と夜との二つに数える仕方で構成されている。(Fowler, Spenser and the Numbers of Time. London: Routledge & Kegan Paul,1964, p.90.)この分割法だと、『祝婚歌』の第1〜第4スタンザの明け方は、結婚式の前日に属することになり、結婚式と同じ1日のサイクルには入らない。第1〜第4スタンザが、それらと対称するスタンザと内容的に必ずしも呼応していない(ハイヤットの分け方だと第1スタンザは第13スタンザの昼と対応する)と言われるが、ファウラーの分け方だとこの批判をうまく解決することができる。もっとも、ファウラーは、ハイヤットの16対8の夏至の分割説を否定しているようであるが、ファウラーの分割は、ハイヤットのそれと必ずしも矛盾しないし、またハイヤットの説を否定する根拠にはならない。スペンサーは、ここで、二通りの昼・夜の分割をだぶらせていると考えることもできる。ファウラーは、夏至と秋分の二通りの昼と夜の長さを認める説を退けているが(Triumphal Forms,p.165n.)、これを退ける根拠はない。確かにハイヤットの恒星時間説は、後に述べるように無理がある。しかし、天の赤道を平均して動く仮の太陽による平均太陽時間は、恒星時間を基に決められるわけで、この両者をどちらかに限定する必要はない。
(3)『祝婚歌』の訳のテキストは、Motohiro
Kisaichi, Spenser: Epithalamion. Kyoto:Yamaguchi-Shoten,1982)によった。
(4)第15と第24スタンザには、短行はそれぞれ二つと一つだけである。
(5)Hieatt, Short Time's Endless Monument,pp.35-39.
(6)Ibid.,p.53.
(7)ハイヤットは、同書(65〜67頁)で、「変転の巻」に基づいて、短行の数「68」について、これに52(周)+4(季節)+12(月)という解釈を提案しているが、これはファウラーの指摘するとおり(Triumphal Forms,p.167.)、恣意的であるとの謗りを免れない。ファウラーは、これに対して、「68」という数よりも長行の92分割のほうに注目し、これが、夏至から秋分までの季節を表わすと考える(Triumphal Forms,p.167.)。今一つ問題なのは、ハイヤットの時間の分割についてである。彼は、短行によって区切られた長行の一つ一つのグループが、4分の1時間を表わすと考え、この推定によって、第16と4分の1スタンザで「夜が来る」とあるのは、結婚式当日のコークでの日没と一致していると考えたことである。だが、この説は、あまりにうがちすぎているように思われる。このハイヤットの分割の難点は、もしも短行が、4分の1時間の刻みを表わすとすれば、全部で72なければならないことである。全体として、ハイヤットは『祝婚歌』と「変転の巻」との関係を重視しすぎている。しかし、これは、それ以後の発見、W.H.Wickertの論文('Structure and Ceremony in Spenser's Epithalamion',ELH,35,1968)やファウラーの前掲書(1970)がまだ出ていなかったことが当然考慮されるべきである。
(8)Fowler, Triumphal Forms,pp.166-68.
(9)Edwin Panofsky, Studies in Iconology: Humanistic Themes in the Art of the renaissance. (New York: Harper & Row,1939) pp.91-92.
『祝婚歌』の273行はホーズのエコーであると指摘されている。
(10)Fowler, Spenser and the Numbers of Time, p.33.
(11)W.K.C. Guthrie, A History of Greek philosophy.( Cambridge University Press,1962.)p.260.
(11)Ibid.,pp.263-65.
(12)Ibid.,pp.222-23.
(14)種村恭子訳『ティマエウス』。『プラトン全集』12巻(岩波書店、1975年)45頁注。
(15)Aristotle: On the Heavens.(268a). Tr.W.K.C. Guthrie, Loeb Classical Library,( London: William Heinemann,1939.)pp.4-5.
村治能就訳「アリストテレス『天体論』」。『アリストテレス全集』4巻 (岩波書店、19678年)3頁。
(16)プロティノス著「三つの原理的なものについて」2〜3章。田中美知太郎、他訳『エネアデス』、田中美知太郎編『プロティノス・ポリュピュリオス・プロクロス』(中央公論社、昭和55年)150〜54頁。
(17)プロティノス「エロスについて」2〜3章。同書258頁。
(18)このポンペイの図版はインターネットによる。
(19)Seneca,"On Benefits",1-3. Seneca, vol.3. Loeb Classical Library,1935, pp.12-17.
(20)Edgar Wind, Pagan Mysteries in the Renaissance (New York:Norton,1958.) p.28.
(21)Ibid.,The Plates 10-11.
(22)Ibid.,p.41ff.なおこの点については以下をも参照。
Marsilio Ficino's Commentary on Plato's Symposium, tr. Sear Reynold Jane, (Columbia: University of Missouri,1944.) p.134,n11.
『プロティノス・ポリュピュリオス・プロクロス』「解題」148頁。
(23)Ficino's Commentary on Plato's Symposium, II-ii,(p.134)
マルシーリオ・フィチーノ著、左近司祥子訳『恋の形而上学』(国文社、1985年)37頁。
(24)フィチーノ『恋の形而上学』1話4章、30〜31頁。
(25)Wind, Pagan Mysteries, pp.37-38;43-44.
(26)Ibid.,pp.73-74.
(27)Ibid.,pp.76-77.
(28)Ficino's Commentary on Plato's Symposium, V-ii(p.167n).
Wind, Pagan Mysteries, p.39n.
フィチーノ『恋の形而上学』98〜99頁。
(29)Wind, Pagan Mysteries, pp.117-19.
(30)『アエネーイス』のここでのヴィーナス・ダイアナを刻んだメダルについては、Wind, Pagan Mysteries, p.75. を参照。また、スペンサーとフィレンツェのネオプラトニズムとの比較については同書45頁。
(31)Wind, Pagan Mysteries, pp.77-78.
(32)アリアドネーの冠と優美の女神たちとの関係については、次を参照。
Fowler, Spenser and the Numbers of Time, pp.225-26.
(33)『妖精の女王』6巻10篇(14〜15スタンザ)と『祝婚歌』(96〜109行)との類似に注意せよ。特に10篇15スタンザの終わりの2行と『祝婚歌』16〜17行とを比較せよ。なお次を参照。Henry G.Lotspeich, Classical Mythology in the Poetry of Edmund Spenser,(New York: Gordon Press,1932) p.4.
スペンサーの『祝婚歌』へ